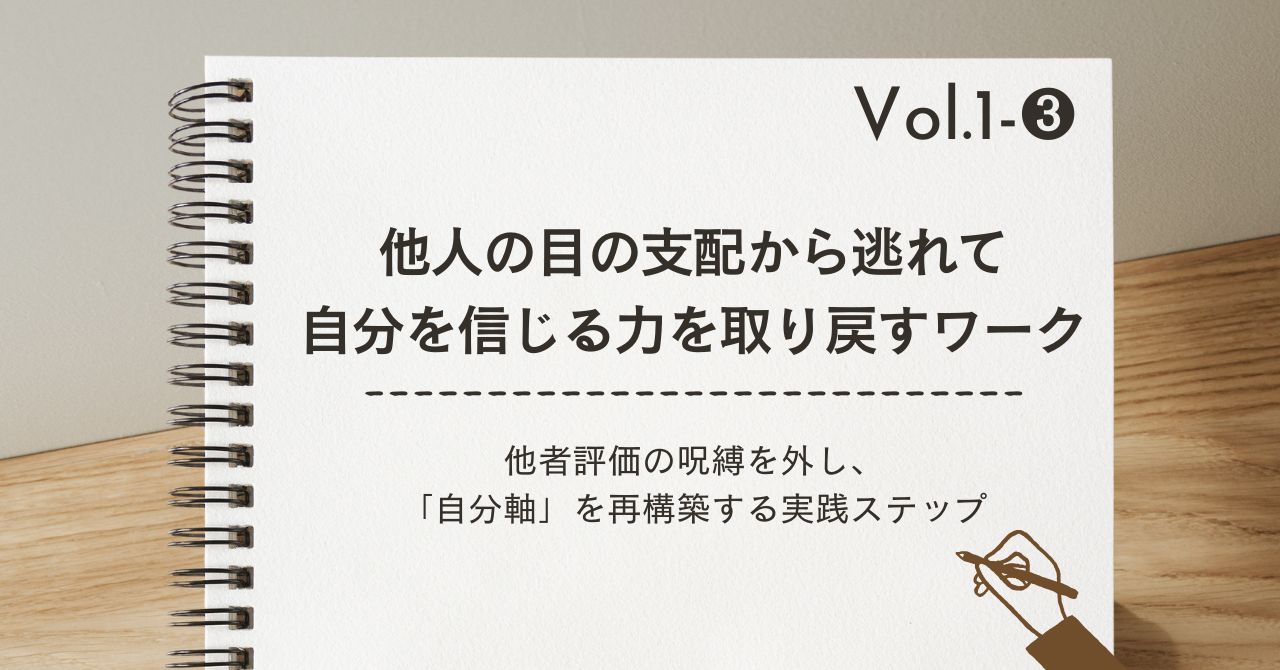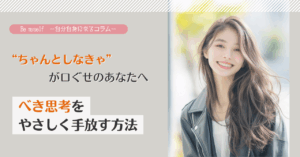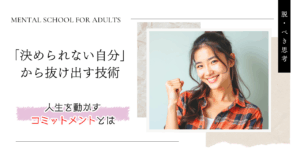他人の目が気になるのは、弱いからじゃない

他人の目、気になりますか?
気になりますよね。直接的な視線はもちろん、反応や無反応、他の人との対応の違い、評価、意見、そして批判。気にならないはずがないですよね。
それは「間違ったことはしたくない、言いたくない」「周囲に嫌な思いをさせたり反感を抱かれて嫌われたくない」という思いが有るからです。そしてこれは人の心理として至極当然な反応です。ただ、自然であるがゆえに無意識に続けてしまい、気づけば「いつも他人の目で自分を測る」ようになっていきます。
ここに、私たちが苦しさを感じる理由があります。
なぜ私たちは他人の目から自由になれないのでしょうか。
もし他人の目を気にせず、自分の基準で選び、話し、動けるとしたら。
そのとき、あなたの毎日はどんなふうに変わるでしょうか。
目次
他人の目が作る「安心」と「不安」
まず、他人の目から私たちが得ているメリットを見ていきましょう。
私たちは毎日数えきれないほどの思考・選択・判断、そして実行を繰り返します。
仕事や家庭問題に関する大きなものだけでなく、朝起きてからまず何をするか、5分の休憩時間をどう過ごすか、たまたま会った知人にどう接するか、こんなことまで全て自分で考えて実行しています。
決断とは、大きなストレスです。そして人は1日に35,000回もの決断を下していると言われています。小さな決断だったとしても、この回数をこなすのは容易ではありません。
そして私たちの集中力や体力、時間は有限です。コスパを意識するのは当然ですね。
決断によるコストを軽減しようとしたとき、非常に便利なのが「他人の目」です。
自分が考えたこと・選ぼうとしていること・やろうとしていることが本当に正しいのかどうかの「後押し」の役目を果たしてくれます。
安全装置のようなものですね。「自分の選択は間違っていない」と感じさせてくれる他者の反応が、心の安定剤になっているのです。
周囲から肯定的な反応を得られれば自信をもって先へ進めます。
決定・実行前ならネガティブな反応を取り入れて修正できるので実行後も安心感があります。
そしてポジティブな結果が得られれば「他人の目を気にしてよかった」と学習しますから、次もまた「他人の目」を意識するようになります。
これが、他人の目の功罪と言えるでしょう。
成功することで習慣化します。安心感は大きなメリットですから多用するようになります。
ですがそのうちどれだけ頑張っても「私が一人でやったことではないから」と、自信を目減りさせていくようになります。
他人の目が合ったからこその成功で、自分だけで来たことではないのだ、と思ってしまいます。
折角頑張って来たのに「このままではだめなのでは」と考えてしまうんですね。
ただ、ずっと他人の目を指標にしてきたので、他のやり方が分からない。八方塞がりになってしまうのです。
逃げても消えない「他人の目」の正体
ある程度の経験やキャリアを重ね、年齢も上がっていくと、「どんなことでも一人でできるようにならなければ」という思いが高まり、更には「他人に良い影響を与えられるようになりたい」とも考えるようになります。
そうすると、いつまでも他人の目を意識し、それが無いと決断が難しい自分に対し不満を持つようになります。この不満はとても必然で成長のためには必要な感情ですが、自分への不満は抱えている当人は辛いものです。
どうにかして自分一人で何もかもできるようにならなければ、と決意します。が、先ほども話したように「他人の目」以外の指標が無いので、やはりそこへ戻ってしまうのです。
他人の目を意識しないようにしよう、だけど自分でどう決断すればいいのか分からない、となった時にパワーアップして現れるのが「べき思考」です。これもまた扱いが難しいことは既にご存じの通りです。
他人の目に頼ってばかりではない、自分だけで判断出来るようなる「べきだ」。
これも変化ではありますが、べきもまた頼り過ぎればいつかまた自分への不信や不満の種になります。
いずれもベースにあるのは、過度に安心安全を求める「不安感」ではないでしょうか。
そして不安と向き合わない限り、私たちは形を変えた「他人の目」から逃れることはできないのです。
他人の目から自由になった先に、待っている4つの変化
①自分の声を聴けるようになる
他人の目に縛られ過ぎないようになると、自分の心の声に気づくことが出来るようになります。
私たちはなぜ他人の目を必要としているのでしょう。それは「安全安心」「正解」が欲しいからですよね。わざわざ他人の目(評価・反応・意見)にそれを求めるのは、自分の心の声に気付けないからです。
本当は「私はーーしたい」と感じているのに、それを覆い隠すように「正しい道を選ぶべきだ」「他人の目に好ましいことをすべきだ」の声が出てきます。なぜならそれが安心安全だからです。
でも「私はーーしたい」を無視し続けていることで、今「他人の目に縛られたくない」「自分自身で判断できるようになりたい」と考えているのですから、そのために必要な「私はーーしたい」に気付けるようになることが大事なのです。
そして自分の「ーーしたい」に気づいてそれに沿って行動するようになると、不満が減っていきます。
②感情の安定性が増す
他人の目とは、メリットだけではないことはご存じだと思います。
自分の考えが間違っていないことを証明したくて他人の目に映したのに、否定されたり批評されたり微妙な反応をされることだってあり得ます。
そうなると途端に自信を失って、どうしたらいいのか分からず途方に暮れてしまい、不安なまま選択・実行してネガティブな結果を引き受ける余裕も無くなってしまいます。
肝心なのは「他人の目に肯定してもらわないと自分は安心して行動出来ない」という考えが思い込みに過ぎないことを知ることです。
他人の目に照合して自分の考えの正しさを確認するのは、本来絶対必要なことではありません。コスパがいいだけです。つまり楽をしているんですよね。その弊害が「ネガティブな反応によるストレス」です。
ちょっと手間がかかったとしても他人の目を使わず自分で判断・実行出来る習慣が作れたら、他人の目による動揺やストレスから解放されます。
自分で決断して実行するのですから、想定外の結果に終わったとしてもリカバリー方法を思いつくのも早いです。
③創造性と行動力が戻ってくる
他人の目というのは「他人の判断基準」です。それは当然あなたの判断基準とは違います。
違う基準を自分の行動や生活に、半ば無理やり当てはめているような状態です。
他人の靴を履いて長時間歩き続けていることを想像してください。とっても窮屈だし、歩くこと自体が辛くなるのは目に見えてますよね。
他人の目から自由になる、ということは、他人の靴を脱いではだしで歩き始めるのと同じです。
それはそれで痛いけれど、他人の靴を履いていた時には分からなかったことが分かるようになります。
それは「自分の現在地」です。どんな道を自分が歩いていたのかが分かるようになります。
すると「どんな靴が自分に合っているのだろう」を考えることが出来るようになります。
そして自分に合った靴、つまり「自分自身の判断基準」が見えてくるのです。
他人の目を使ってコスパよく安心を手に入れていた時には無かった創造性が戻ってきます。
そして自分らしい判断基準が分かれば、他人の目に縛られず、思ったように自由に行動できるようになり、行動範囲が広がり、経験を積むことが出来ます。
失敗しても「試行錯誤」と捉えることが出来るので、学びや挑戦が楽しくなります。
どんどん成長して行けるようになるのです。
④「自分の人生を生きている」という実感が戻る
他人の目から自由になるためには、それに代わる「自分自身の判断基準」を求めるようになります。
まさにこれが「自分軸」です。
自分が好きなこと、大事にしたいこと、心地よいこと、正しいと信じられること、といった「価値があると思えること」に沿って行動出来るようになります。
すると、自分の生活が一変します。
環境、人間関係、計画、目標、趣味、余暇、仕事、勉強。
全てが「自分らしいもの」で埋め尽くされるようになります。
自分らしい人生だから、多少困難やトラブルがあっても「自分ならどうやって乗り越えようか」という前向きな見方をすることも容易です。
自分の人生を生きているんだ、という実感を得ることが出来るようになるのです。

まとめ:他人の目を「敵」ではなく「鏡」にする
他人の目を気にしてしまう自分を責める必要はありません。
むしろそれは、「安心したい」「間違いたくない」という、あなたの正直な願いが働いている証拠です。
ただし、他人の目を「絶対的な評価軸」としてしまうと、いつしか自分の感覚や判断がかすんでいきます。
他人の評価は、あなたを裁くものではなく、今のあなたの心を映す鏡のようなものです。
たとえば、誰かの言葉に強く反応した、としましょう。
そこには「自信を持ちたい」「認めてほしい」という、あなたの大切な願いが隠れています。
それに気づけた瞬間、他人の目は「敵」ではなく「味方」へと変わります。
他人の評価を情報として受け取りながらも、最終判断は「自分の基準」で下す。
この小さな積み重ねが、あなたの世界を静かに、でも確実に広げていきます。
もし今、「自分の軸で生きたいけれど、どうやって見つければいいのか分からない」と感じているなら、次のステップとして「自分軸を育てるワーク」に取り組んでみませんか?