“ちゃんとしなきゃ”が口ぐせのあなたへ:べき思考をやさしく手放す方法

私たちは誰でも「~すべき」という、いわゆる「べき思考」を持っています。
しかも1つや2つではなく、あらゆる場面でそこに適用されるべきを持っています。
■他人の気分や感情に配慮すべき
■年齢や性別に相応しい振る舞いをすべき
■常に努力すべき
■人に迷惑をかけないようなんでも出来るようなるべき
他にもきっとたくさんあるでしょう。
こうして眺めてみるとどれも全部尤もなことに見えます。なのにどうして「べき思考が自分を苦しめる」と感じるのでしょうか。
目次
- べき思考は『自分の考え』ではないから辛い
- べき思考が強すぎることでのデメリット
- べき思考も「無駄」「悪」なわけではない
- べき思考を手放すとどうなれる?
- まとめ:べきを手放すことはモチベーションを手に入れること
- ≪次の一歩へ≫
べき思考は『自分の考え』ではないから辛い
べき思考ってどこから生まれると思いますか?
自分がそう思うから、というのは、半分正解で半分違います。
自分がそう思うのは、これまでの人生で「べき思考」に繋がることを、周囲からたくさん言われ続けてきた結果です。
親、友人、知人、先生、上司、先輩。
更には周囲の期待や社会的役割や望ましさ。
そう言ったものが何度も積み重なった結果生まれたのがあなたが持つ『べき』です。
このべき思考を行使するのは自分の意思ですが、べき思考の中身は『他人の意見』です。
自分の考えだ、と断言出来ないから、べき思考は辛いのです。
べき思考が強すぎることでのデメリット
上記に事例を挙げたように、べき思考は大抵正しいことを述べています。
それなのに、べき思考は、大抵は私たちの行動の足を引っ張ります。
その理由はいくつかあります。
①自信喪失につながる
べき思考を「正しい」と思うほど、それと合致しない、または合致しない点が多々見受けられる自分に対する評価が下がります。つまり自信を失ってしまうんですね。
②人間関係の悪化
べき思考は自分の行動や思考にだけ適用されるわけではありません。他者に対しても向けられます。
自分が「他人の気分や感情に配慮すべき」と強く思うほど、他者がそれにそぐわない振舞をしている時に、その人を「間違い」と断じてしまいます。当然良くない印象を持ってしまうでしょう。
結果としてその人との関係性が悪化します。
③思考が硬直化する
べき思考を正しいと思うほど、他の視点から考察したり、違う考え方を許容できなくなります。つまり思考が硬く狭く柔軟性を失ってしまうのです。
結果として、自分の未来の可能性を狭めることに繋がってしまうのです。
べき思考も「無駄」「悪」なわけではない
と、ここまで聞くと「内容は正しくてもやっぱりいいこと無しなのでは」と思われたかもしれません。
しかしそういうことではないのです。
先ほどから何度かお話していますが、べき思考はどこから来たのでしょう。
どんな内容でしょう。
その場その場で自分にとっての「重要な他者の声」だったり「社会からの望ましさ」が自分の内側に蓄積されて出来上がった「生きる上での方針」、それがべき思考です。
そしてこれを使う場面は、自分がどう行動すればいいのか悩む場面が多かったのではないでしょうか。
つまり、べき思考はこれまでの経験の中で幾度か私たちを守ったり導いたりしてきたのです。
ただ、それだけを強く信じすぎたり多用しすぎることで、<2>で述べたようなデメリットを生んでしまうのです。
べき思考そのものが悪いわけではない、ただ他の考えを取り入れる余裕を作り、もっと私たち自身を成長させるためには、適宜手放していく必要があるのです。
べき思考を手放すとどうなれる?
正しいしこれまで役に立ってきた「べき思考」、だけど持ち続けることで自分の未来を狭めることもある「べき思考」。
これを手放すと、どんなメリットがあるでしょうか。
①自分に自信が持てるようになる
「べき思考」の中身は他人からの言葉です。べき思考に従って判断・行動しているうちは、どこかで『誰かの言う通りにしている』感がぬぐい切れません。
その状態から解放されます。自分がどうしたいのか、どうすることが最適なのか、を考えるようになるので、その結果が良いものであれば自分の実績として捉えることが出来ます。
それ以前に「自分の考えに沿って行動出来た」ということ自体が、自己肯定感を高めてくれます。
②他者への共感が高まる
他人に対しても適用されてしまうのが「べき思考」の怖いところです。どんな理由があって他者がそうした(べきに反すること)のか、を考えることもほとんどありません。
べき思考から離れて他者と関わると、相手の行動を「良い・悪い」で判断することが無くなります。もし相手の判断や行動が自分が思っていたものではなくても「この人はどうしてこういう判断をしたのだろう」という疑問を持つことが出来、「この人なりの理由があってやったことなのだろう」と許容することが出来ます。
つまり、他者に対して共感し受け容れることができるようになるのです。
③思考が柔軟になる
「べき思考」が強すぎると、そこから少しでも外れると居心地が悪くなります。そしてずれている自分を「劣っている」と感じたり「間違ったことをしている」と責める気持ちまで湧いてきてしまいがちです。
その「縛り」から解放されます。そして「他の人だったらどうするんだろう」「今は前回とは状況が違うのだから」と思考の条件を緩めることができるようになります。そこから更に「あの人に手伝ってもらおう」「今回はこの程度で十分だな」のような、具体的な対策も思い浮かぶようになります。
その結果、「べき」時代には得られなかったような結果を手にすることも可能になるのです。

≪おすすめブログ≫心の柔軟性を高める5つのステップ
まとめ:べきを手放すことはモチベーションを手に入れること
「~すべき」は、私たちをある程度動かしてくれます。
「やらなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」という思考は、一時的には行動の燃料になります。
でも、その燃料はすぐに切れてしまうのです。
なぜなら「べき思考」の原動力は、恐れや不安だから。
「怒られたくない」「嫌われたくない」「認められたい」といった気持ちが、あなたを動かしています。
だから結果が出ても心は晴れず、達成感も長続きしません。
一方、「~したい」で行動できたとき、私たちは自然に動けます。
その動機は安心や好奇心、愛情や楽しさなどの「プラスのエネルギー」だからです。
たとえ同じ行動でも、「~すべき」でやるのと「~したい」でやるのでは、心の消耗度がまるで違います。
だからこそ、「べきを手放す」というのは、何も怠けることでも甘えることでもありません。
あなたの本来のモチベーションを取り戻す作業なのです。
“私はどうしたい?”
この問いを自分に向けられるようになるほど、
人は自然体で成果を出せるようになります。
≪次の一歩へ≫
ここまで読んで「頭ではわかるけど、実際にどう手放せばいいの?」と思われた方へ。
この続きは、実際にワーク形式で「自分の中のべき思考」を見つけ、それを「私は~したい」へ書き換えていく、有料コンテンツで解説しています。
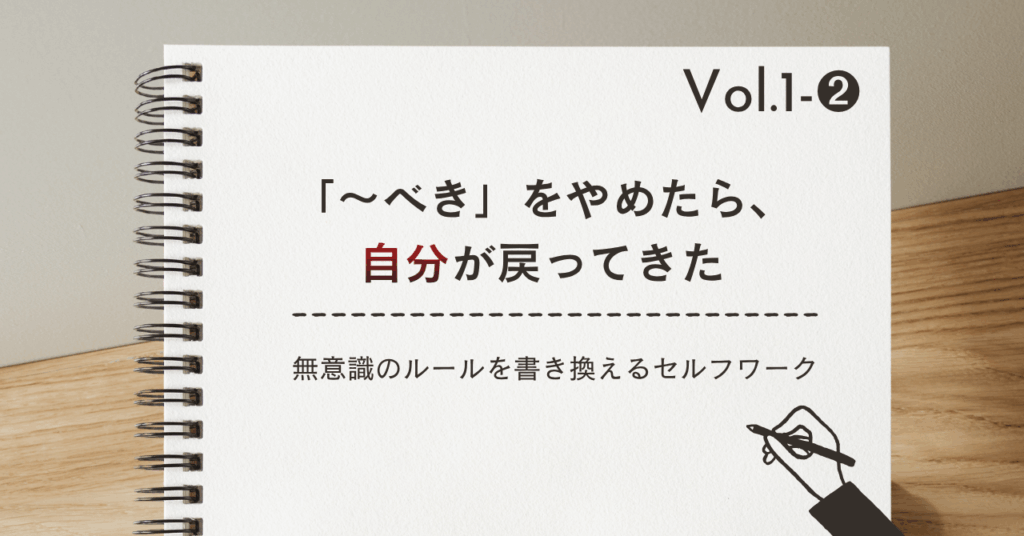
『~べきをやめたら、自分が戻ってきた』
無意識のルールを書き換えるセルフワーク付き(約4600字)
自分を縛っていた“他人の基準”を手放し、“自分軸”を取り戻す実践編です。

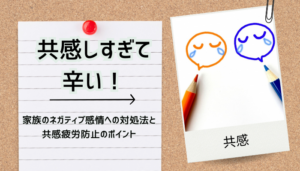

““ちゃんとしなきゃ”が口ぐせのあなたへ:べき思考をやさしく手放す方法” に対して1件のコメントがあります。