“家族だから分かる”は本当? うつ病の家族との適切な距離感とは
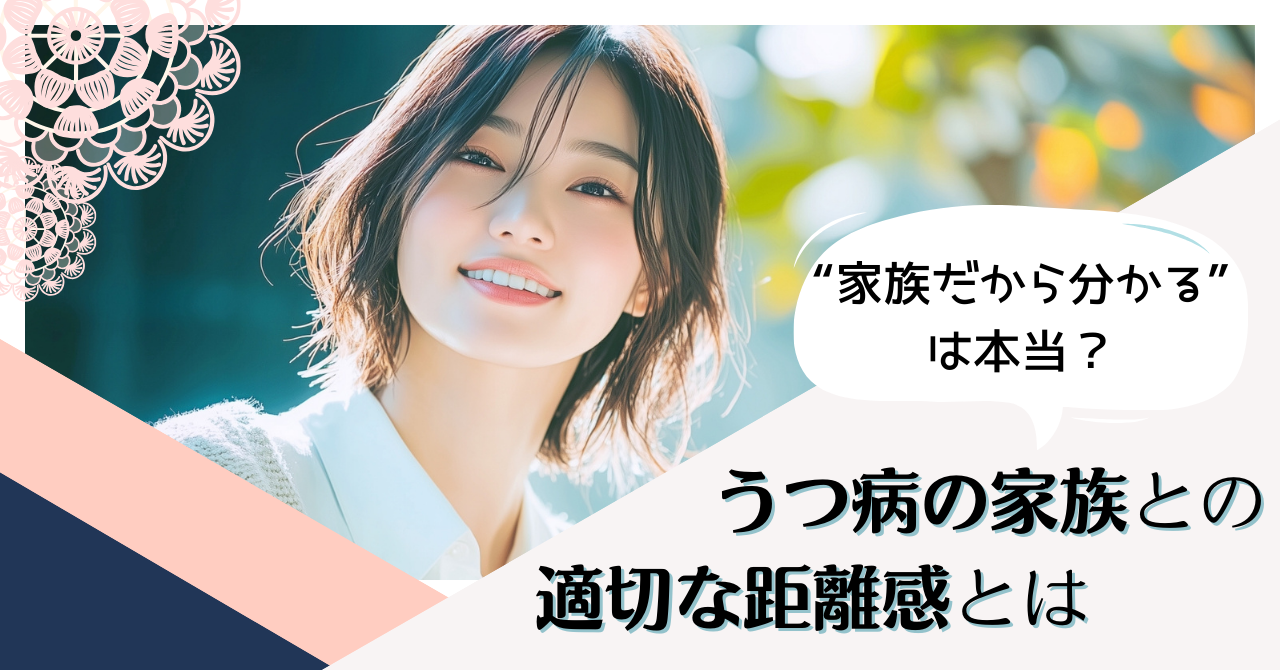
うつ病の家族との距離感、考えたことありますか?
「家族だから、分かってあげたい」「自分が支えなきゃ」
そんな想いで心の病を抱える家族をケアする中で、知らず知らず自分を追い詰めていませんか?
本記事では、支えたい気持ちが時に“支えすぎ”になってしまう理由と、心の病を回復へと導くために必要な“距離感”と“ケアラー自身のケア”について心理的視点から紐解きます。
共倒れを防ぎ、希望あるケアを続けていくためのヒントをお届けします。
目次
「家族だからわかる」は本当にそう?
共感と理解は必要。でも“わかろうとしすぎる”ことの危険
家族は確かにとても特別な関係です。血がつながっている、そうでなくても衣食住を共にするということは「人生を共有している」関係です。
常に一緒だからいいところだけじゃなく、お互いの欠点だって知っています。
ケンカもするけど、それでも一緒にいる。他の友人知人とは質が違う親密さです。
とはいえ、自分ではない人間=他人なんですよね。
この認識は結構忘れられがちです。
近しすぎるあまりに、相手(家族)のことも自分自身のことと同じくらいわかっている、と錯覚してしまうことがあります。
誤解されやすい「本人のために」の言動とは?
特に相手が病気、更にはうつ病などの精神疾患だと「分かる」が暴走することがあります。
精神疾患は病気の部分が目に見えません。患者本人がどう感じているか、が全てといっていいでしょう。
そして本人もスムーズに気持ちを話せません。そういう病気(思考力の低下)なので仕方ないですよね。
思考力や意欲が激減しているから、自分の病気について調べる余力はありません。何をするのが良いのか、何はしないほうが良いのか、は、知らなければ間違いやすい。だからうつ病は長引きやすいとも言えます。
その状況では、家族は本人の代理になろうとします。家族が思うだけでなく周りもそう仕向けてきます。
そして出てくる「本人のため」という姿勢と考え方、言葉は、本当に本人のためになっているのか分からないものになってしまいがちなのです。
適切な距離感とは?:心理的・物理的距離を整理する
「距離を取ること=冷たい」ではない
家族として踏み込み過ぎたり自他の境界があいまいになることが、支える家族の頑張りを逆効果にしてしまうことがあります。
ではどうしたらいいのでしょう。
適切な距離を保つこと、ですよね。
ただこの「適切」というのが曖昧で抽象的でわかりづらい。
料理で「適量」ってありますけど、だからどれくらい?!って思うのは私だけじゃないと思います。
0か100かで考えてしまい、「距離をとるって見捨てることでは?」と考えてしまいます。
日本には「つかず離れず」という言い回しがありますよね。あれは非常に言いえて妙です。
くっつき過ぎるから自他の境界線が分からなくなり、相手の気持ちを確認もせず「~~だろう」と思い込んでしまう。
相手には相手の気持ちがあることを忘れず、しかし必要なタイミングで協力できる距離感を見極めることが大事なのです。
心のスペースを確保することで見えてくるもの

相手と自分の間に一定の距離が出来ることで、いくつかメリットが期待できます。
まず一つは「自分の責任ではない」と思えること。
ぴったりくっついて相手がやることなすこと・相手が出来ないこと不足していることを全部自分がやらなきゃいけない、と考えるから、イライラするしコントロールしようとしてしまいます。
相手との間に心理的な距離をとることで、「自分が全部やらなきゃ」という思い込みから解放されます。
二つ目は「違う見方が出来るようになる」という点です。
どんなに大事なことでも、近すぎれば視野が限定されて全体が見えなくなってしまいます。
心の病の家族をケアする場合は、相手の「出来ないところ・不足していること」にばかり目が行ってしまって「出来ていること・大丈夫なこと」に目が行きません。
自分が何とかしなきゃ、というポジションから離れることで「意外と大丈夫かもしれない」と思える瞬間が増えていきます。
“共倒れ”を防ぐための距離感のヒント
ケアする側と患者の距離感が近すぎることで起きる問題は色々あり余すが、その最たるものが「共倒れ」です。
少しでも早く元気になって欲しい、だけど今は無理をさせたくない、という気持ちが、今現在のケアと未来への備えの「二足の草鞋」をケアラーに履かせます。
もちろんケアラー自身も自分の生活(仕事、趣味、人間関係)がありますから、草鞋は二足どころではありません。あっという間にキャパオーバーになります。
ですがケアラーは未来への不安を回避したいあまり、自分の不調には見てみぬふりをします。結果、二人とも心身に不調をきたし生活が回らなくなる「共倒れ」状態に至ってしまいます。
適切な距離感を保つことで、共倒れを防ぐことが出来ます。
■私が何もかもやらなければ、この家族はダメになる
■私は家族なんだから、彼・彼女の辛さは一番理解してあげられる
■彼・彼女にとっては私だけが頼りなんだからしっかりしなきゃ
この気持ちが強すぎること自分のことをケア出来ないし、周りに助けを求められないし、本当は本人出来ることがあってもそれを認められない。
永遠に自分一人で頑張らなきゃいけなくなってしまうのです。

≪おすすめの記事≫バウンダリーで心を守る:他人の感情に支配されないために
支援と依存の境界線を知る
支えすぎることが「回復の妨げ」になるケース

頑張って支えなきゃ!と思っている家族にとって「支えすぎ」という状態は想像しずらいかもしれません。
やり過ぎて何が悪いのか、が、まず分からないですよね。
病気になった家族に献身的に尽くすことは、基本的に良いことですから。
ただし、一つ盲点があることを思い出しましょう。
『心の病は目に見えない』という事実です。
目に見えないから観察を怠ると回復度が分からなくなります。
骨折した人が治ったら立って歩く練習をしないと筋肉が戻ってこないのと同様に、心の病も必ず回復していきますから、それに合わせて本人が考えて選んで決断して行動出来るようにならなきゃいけない。
しかし献身的に支えすぎることで、その邪魔をしてしまうのです。
本人の回復力を信じる姿勢が、真の支援になる
もちろん献身的なケアの動機は『家族への親愛』と『気遣い』です。それを否定しようというのではありません。
ケア生活が続くと、しんどいながら家族もそれに慣れていきます。
慣れってすごく安心しますよね。慣れるまで大変だったからこそ、変えることが怖くなる。
ネガティブな変化だけがストレスになるわけではありません。内容がポジティブでも変化に繋がればストレス化します。
家で療養していることに本人も家族も慣れて安定すると、症状が回復して出来ることが増えていきます。そうなれば当然『次のステップ』を見据える必要があります。
その時に変化を拒絶してしまうと、回復を止めてしまうことになりかねません。
変化を拒否するより『これからもっと元気になっていく、今はその途中なのだ』と、病気本人の回復を信じることこそが、本当に必要なケア・支援なのです。

≪おすすめの記事≫エンパワメント: 家族が力を発揮するためのアプローチ
自分のケアを優先してもいい理由
自分の健康が、家族の安定にもつながる
私は心の病になった家族をケアする人(=メンタルケアラー)を支援する専門家です。
常々言っているのは「何よりもまずはケアする人の心身の健康と安定が大事」と言うことです。
しかし実際は逆になっていますよね。
「まずは彼・彼女(病気になった本人)が元気になることが大事。本人が元気になれば自分も自動的に元気になれるんだから」
と考えて、自分自身のことはほったらかしになっていませんか?
これが短期間、または有期であることが確実なら、何とかなるかもしれません。
しかし心の病はそう簡単に回復しません。運よく数ヶ月で社会復帰できたとしても、それは「病気になる前と完全一致」ではありません。悪化・再発しないための配慮は必須なのです。
それだけ長期にわたる可能性があるのに、自分のケアは「本人がケアを不要になった後」までお預けにしていいものでしょうか。無理ですよね。
そして支えてくれる人なしには病気の回復は一層困難になります。
まずはケアラー自身が自分の心身をケアする方法を確立してこそ、ケア生活が成立するのです。
「休む勇気」「助けを求める力」が求められている
ではケアラーが自分自身をケアする、とは、一体どういうことでしょうか。
ストレス解消やリラクゼーションを取り入れる、健康に気を付ける、などが思いつくでしょう。もちろんこれらもどんどんやっていただきたいです。
ただ、それだけで乗り越えようととするのは難しいです。
一つ質問です。
「自分が休む・遊ぶこと」「周りに助けを求めること」は、『悪いこと』『やってはいけないこと』と、罪悪感を感じていませんか?
ケアラーが心身に負担をため込む最大の理由が、この根拠のない罪悪感なのです。
罪悪感を感じているから、休むことが出来ないし、好きなことを楽しめないし、周りに助けを求められないのです。
なぜ自分はこれらに対して罪悪感を感じてしまうのか。
その根っこに何があるのか。
突き詰めれば、ケアそのものとはあまり関係ない古い記憶や経験から得た『マイルール』が浮かび上がってくるでしょう。心理学的に言うと『認知の歪み』です。
ケアラーは、大事な家族を支える生活の中で、自分自身と向き合い直す機会に何度も遭遇します。疲労と多忙でスルーしてしまう・することが出来てしまいますが、それは何度もケアラーの前に立ちふさがります。
自分が自分のケアに対し罪悪感を抱いてしまうその理由に、じっくり向き合うことをお勧めいたします。
ソーシャルサポートを活用することの大切さ

ソーシャルサポートとは「社会的支援」、つまり家族以外の人達から得られる支援のことです。
障がい者支援のような公的な専門支援、病院で受ける治療から始まって、別居している親やきょうだいからの気遣いや手伝い、友人が心配してくれたり愚痴を聞いてもらったり、といったことまで含まれます。
うつ病や精神疾患の場合、残念ながらまだ偏見が強く残っています。偏見を持たずに『大変だね』と普通に話を聞いてもらえるだけで安心します。これもソーシャルサポートと言えるでしょう。
こうした支援は受け取っていいのです。受け取るべきです。そして活用したほうが絶対に自分達のメリットになります。
時間やお金的に助かるだけではありません。
■自分達は周囲に拒絶されるような存在ではない、と実感する
■助けを求めたら応えてもらえる、という体験が出来る
■助けを求めることが出来た自分に自信を持てる
といった効能もあります。
病気になった、その家族を支える生活の一番の敵は『孤立感』です。それが高まることで家族は「自分達家族だけでどうにかしなければ」と考えて無理をし過ぎてしまいます。
社会的支援は、大きなものから小さなものまで、しっかり受け取って活用しましょう。

≪おすすめの記事≫家族の認知の歪み―「私が頑張らなきゃ…」が負担を増やしていませんか?
おわりに:家族の距離は“愛”のかたち
家族だからこそ「わかってあげたい」と思う気持ち。それはとても大切で、あたたかい想いです。
しかしその気持ちが強すぎると、「わかっているつもり」「支えているつもり」が本人の回復を妨げてしまうことがあります。
この記事では、心の病を抱えた家族との関わりの中で、“適切な距離感”を保つ重要性や、“支援”と“依存”の境界線を知ることの大切さをお伝えしました。
何よりもまず、ケアラー自身の心身の安定が土台になります。
罪悪感を手放し、自分のケアを優先することは、決して“わがまま”ではありません。
それは、大切な人を長く支えるために必要な“勇気ある選択”なのです。



